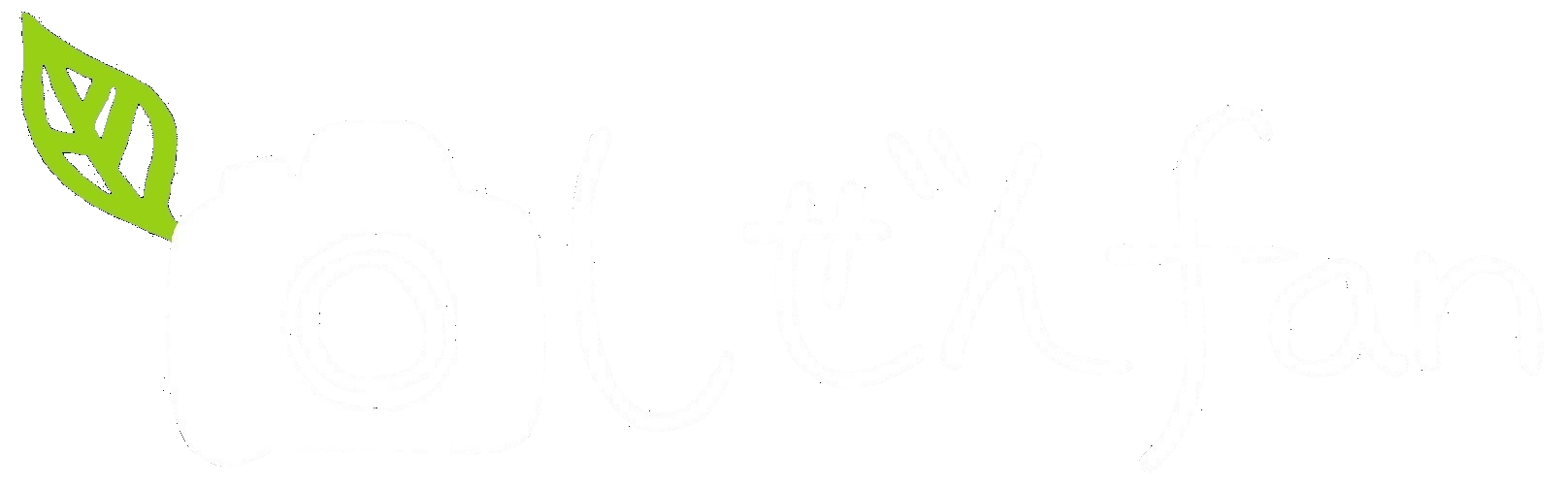こんにちは! 2020年6月7日現在、県境越え自粛中の自然観光ファン、Pollyと申します。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
私は、この籠りがちな時期を利用して、これからの旅をより豊かなものにするための自習活動中です。
ということで今回は、日本の山事情を知る企画の続編。2020年6月3日時点で国土地理院より公表されている「日本の山岳標高一覧(1003山)」を元に、エリア別標高ランキングを作成したいと思います!
前回から引き続きの方も、今回だけの方も、短い間ですがどうぞよろしくお願いいたします☺
目次
「日本の山岳標高一覧」について
まずは、この記事のデータソースとなっている「日本の山岳標高一覧」について軽く触れておきたいと思います。
詳しくは前回の記事内でご説明しておりますが、この一覧は国土交通省・国土地理院が平成3年度(1991年度)に発表し、以降改訂され続けているものです。
「日本の主な山岳標高」のページから誰でもアクセスし、全国各地の「1003」の山の名称および標高を確認することができます。
「1003」とは書いてありますが、一つの山で峰がいくつもある場合はそれらも載っていたりするので、私が調べた限りでは、実質は「1059山(峰)」です。
(例えば北海道の「大雪山」からは旭岳、北鎮岳、白雲岳、愛別岳、黒岳の5つが載っていますので、1山で5枠取っているということになります。)
一覧に載っていない峰や山もあり、そのあたりの基準は素人の私には分かりかねますが、ここでは「1059山(峰)」を材料に話を進めていきたいと思います。
エリアごとの「高い山トップ10」
前回の記事を読んで下さった方、中部地方にお住まいの方、日本の地理をよく知る方々はご存じの通り、2,500mを超えるような高い山は、そのほとんどが中部地方に集中しています。
そんなわけで、「日本の高い山ランキングトップ20」を作ってみても、それは見事に「中部地方の高い山ランキング」と被ります。
さらに言うと、トップ20に登場するのは「長野・山梨・岐阜・静岡・富山」の5県のみです。
日本アルプス、恐るべし。
それはそれで素晴らしいことですが、これでは他のエリアの山々の出る幕がありません。中部にしたって、他にはどんな高い山があるのか、地域ごとの最高峰はどこなのか、知りたくありませんか?
というわけでここからは、エリア版の高い山トップ10を掲載していこうと思います!
ご紹介するエリアの括りは以下の通りです。
- 北海道
- 東北…青森、秋田、山形、岩手、宮城、福島
- 関東…栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川
- 北陸…富山、石川、福井
- 関西…滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫
- 中国…鳥取、島根、岡山、広島、山口
- 四国…香川、愛媛、徳島、高知
- 九州…福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
※三重県はここでは東海の仲間とさせていただきました。また、沖縄には高い山がないため割愛。
※スマホをご利用の方は、横スクロールでランキング表の全体を見ることができます。
それでは、北から順に下っていきましょう!
北海道の高い山
まずは北海道です。
| 山名<山頂名> | 標高 | 所在地 | ||
| 1 | 大雪山<旭岳> | 2,291m | 東川町 | 石狩山地 |
| 2 | 大雪山<北鎮岳> | 2,244m | 東川町 | 石狩山地 |
| 3 | 大雪山<白雲岳> | 2,230m | 美瑛町 | 石狩山地 |
| 4 | トムラウシ山(富良牛山) | 2,141m | 美瑛町・新得町 | 石狩山地 |
| 5 | 大雪山<愛別岳> | 2,113m | 上川町 | 石狩山地 |
| 6 | 十勝岳 | 2,077m | 美瑛町・上富良野町・新得町 | 石狩山地 |
| 7 | 美瑛岳 | 2,052m | 美瑛町 | 石狩山地 |
| 幌尻岳 ぽろしりだけ | 2,052m | 平取町・新冠町 | 日高山脈 | |
| 8 | オプタテシケ山 | 2,013m | 美瑛町・新得町 | 石狩山地 |
| ニペソツ山 | 2,013m | 新得町・上士幌町 | 石狩山地 | |
| 9 | 大雪山<黒岳> | 1,984m | 上川町 | 石狩山地 |
| 10 | カムイエクウチカウシ山 | 1,979m | 新ひだか町・中札内村 | 日高山脈 |
| 11 | 石狩岳 | 1,967m | 上川町・上士幌町 | 石狩山地 |
| 12 | 忠別岳 ちゅうべつだけ | 1,963m | 美瑛町・上川町 | 石狩山地 |
| 13 | 戸蔦別岳 とったべつだけ | 1,959m | 新冠町 | 日高山脈 |
| 14 | 音更山 おとふけやま | 1,932m | 上川町・上士幌町 | 石狩山地 |
| 15 | 上ホロカメットク山 | 1,920m | 上富良野・南富良野町・新得町 | 石狩山地 |
※所在地のうち、町名はWikiperia等で個別に調べたものです。
トップ10には大雪山一味が席巻しており、他の山がほとんど登場できませんでしたので、北海道は特別に「トップ15」にしてみました。
大雪山系にはもっとたくさん峰があるはずですが、なぜか「日本の山岳標高一覧」に入っているのは上記の5岳だけです。
2019年の“今年の山”だった「緑岳」の標高が改訂され、2020年もまた標高年続行か? という話をHBCラジオで聞いたことがあったので、載っていないのは寂しい気分です。(私は一応、元北海道民です。)
そして、ここではどうでも良い話ですが、旭岳でのスノーボードは本当に最高!で、黒岳のリフト頂上からの眺めも最高!です。よね!

というわけで、北海道で高い山の多い地域といえばやはり、中央部に広がる「石狩山地」であることが分かりました。
特に美瑛町は、「美瑛の丘」や「青い池」のイメージばかりありましたが、北海道を代表する山々がいくつもあったとは。
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
ランキングにはちらほら顔を出している「日高山脈」は、北海道で唯一の山脈です。Wikipediaによると、“狩勝峠側の佐幌岳から襟裳岬までを南北に貫いて”おり、“長さは南北およそ150km”であるとのこと。
確かに札幌と帯広を結ぶラインより南側は道路網が発達しているとは言い難く、気軽には出かけられないイメージです。日高山脈がどーんと横たわっているからだったんですね。
山々の位置に注視しつつあらためて地図を見てみると、自分では認識すらできていなかったことが浮かび上がってきたりして、なかなか面白いものです。
【PR】人気ブランド patagoniaやTHE NORTH FACEの新作アイテムを多数取り扱い中!東北の高い山
次は東北を見てみましょう。
| 山名<山頂名> | 標高 | 県 | 所在地 | |
| 1 | 燧ヶ岳<柴安嵓>ひうちがたけ しばやすぐら | 2,356m | 福島 | 南会津・尾瀬 |
| 2 | 鳥海山<新山>ちょうかいざん しんざん | 2,236m | 山形 | 出羽山地 |
| 3 | 駒ヶ岳(会津駒ケ岳) | 2,133m | 福島 | 南会津・尾瀬 |
| 4 | 飯豊山 いいでさん | 2,105m | 福島 | 飯豊山地 |
| 5 | 帝釈山 たいしゃくざん | 2,060m | 福島 | 南会津・尾瀬 |
| 6 | 岩手山 いわてさん | 2,038m | 岩手 | 奥羽山脈北部 |
| 7 | 西吾妻山 にしあづまやま | 2,035m | 山形・福島 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) |
| 8 | 北股岳 きたまただけ | 2,025m | 山形 | 飯豊山地 |
| 9 | 月山 がっさん | 1,984m | 山形 | 朝日山地 |
| 10 | 西吾妻山<西大巓 にしだいてん> | 1,982m | 山形・福島 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) |
県でいえば、高い山が一番多い県は福島県、二番は山形県、ということが分かりました。
ただ、北海道のように「どの山地・山脈が独り勝ち」というようなことはなく、東北各地に散らばっているような印象です。
福島の南、群馬と新潟とに跨る「尾瀬」や、同じく南会津の秘境「帝釈山脈」、秋田と山形の県境付近の「出羽山地」、福島・新潟・山形の3県に跨る「飯豊山地」、そして、東北地方をずらりと縦に走る「奥羽(おうう)山脈」。
日本百名山.netによると、奥羽山脈は“日本の東北地方の中央部を、青森県から栃木県にかけて南北に延びる日本最長の山脈”だそうです。長さは約500kmもあります。
その最高地点が岩手県の「岩手山」で、有名な「八甲田山」や「蔵王」、「磐梯山」などもすべてこの“奥羽山脈シリーズ”。
加えて「越後山脈」というものもあるらしく、どこからどこまで、どれがどこに属するのか、私のような素人には混乱の極みです。
とにかく広い山景色が美しい東北地方、大好きです。

関東の高い山
次は関東地方です。
| 山名<山頂名> | 標高 | 都県 | 所在地 | |
| 1 | 白根山 しらねさん(日光白根山) | 2,578m | 栃木・群馬 | 那須・日光 |
| 2 | 浅間山 あさまやま | 2,568m | 群馬 | 苗場山・白根山・浅間山 |
| 3 | 男体山 なんたいさん | 2,486m | 栃木 | 那須・日光 |
| 4 | 女峰山 にょほうさん | 2,483m | 栃木 | 那須・日光 |
| 三宝山 さんぽうやま | 2,483m | 埼玉 | 関東山地 | |
| 5 | 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ | 2,475m | 埼玉 | 関東山地 |
| 6 | 女峰山<大真名子山 おおまなごさん> | 2,376m | 栃木 | 那須・日光 |
| 7 | 太郎山 たろうさん | 2,368m | 栃木 | 那須・日光 |
| 8 | 四阿山 あずまやさん | 2,354m | 群馬 | 苗場山・白根山・浅間山 |
| 9 | 女峰山<小真名子山 こまなごさん> | 2,323m | 栃木 | 那須・日光 |
| 10 | 横手山 よこてやま | 2,307m | 群馬 | 苗場山・白根山・浅間山 |
関東は中部地方に次いで高い山の多い地域ですので、26位くらいまではずっと2,000m超えです。
こちらにも先ほどの「越後山脈」や「三国山脈」、「足尾山地」などいくつか山地があり、特に栃木県西部(日光)と群馬北西部に高い山が集まっているようです。
そこに埼玉県西部の「奥秩父」が加わるという感じ。
私事で恐縮ですが、私は関東周辺の地理には大変疎く、関東平野の西側(赤石山脈の東側)に「関東山地」なる山塊があるなんて、今の今まで知りませんでした…。
なんでも、北の「秩父山地」と南の「丹沢山地」に分かれているそうで。
上のランキングで4位となっている「三宝山」は、関東地方にある秩父山地の中では一番高い山ですが、秩父山地自体の最高峰は、山梨の「北奥千丈岳(2,601m)」なんだそうです。
勉強になりました!

北陸の高い山
中部地方全体のランキングは前回の記事の「日本の高い山トップ20」と丸被りですので、ここではさらに地域分けをして、北陸3県のみをご紹介したいと思います。
(甲信越と東海はどちらも全国順位と大差ないため、省略させていただきます。)
| 山名<山頂名> | 標高 | 県 | 所在地 | |
| 1 | 立山<大汝山>たてやま おおなんじやま | 3,015m | 富山 | 飛騨山脈北部 |
| 2 | 剱岳 つるぎだけ | 2,999m | 富山 | 飛騨山脈北部 |
| 3 | 水晶岳(黒岳) | 2,986m | 富山 | 飛騨山脈北部 |
| 4 | 白馬岳 しろうまだけ | 2,932m | 富山(・長野) | 飛騨山脈北部 |
| 5 | 薬師岳 | 2,926m | 富山 | 飛騨山脈北部 |
| 6 | 野口五郎岳 | 2,924m | 富山(・長野) | 飛騨山脈北部 |
| 鷲羽岳 わしばだけ | 2,924m | 富山(・長野) | 飛騨山脈北部 | |
| 7 | 鑓ヶ岳 やりがたけ | 2,903m | 富山(・長野) | 飛騨山脈北部 |
| 8 | 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ | 2,889m | 富山(・長野) | 飛騨山脈北部 |
| 9 | 別山 べっさん | 2,880m | 富山 | 飛騨山脈北部 |
| 10 | 龍王岳 りゅうおうだけ | 2,872m | 富山 | 飛騨山脈北部 |
見事に全てが「飛騨山脈」、そして富山県の独り勝ち(?)となりました。
富山の街からは当たり前に「立山連峰」を望むことができ、初めて訪れたときはあまりの日本離れした景色に度肝を抜かれたものです。

なんとなく、以前住んだことのあるニュージーランド南島の「クイーンズタウン」と景色が似ているなと思いました。
4位の「白馬岳」は、「はくば」と読むかと思いきや、「しろうま」が正式な読み方なんですね。しかし、村の方は「はくばむら」で良いんだそうで、山の方も今では「はくばだけ」と呼ぶ人も多いようです。
地元の人には常識であろうことでも、九州出身者の私が「ん?!」と二度見したのが、6位の「野口五郎岳」。
あの歌手の方にちなんだのかと一瞬思いましたが、そんなに最近名付けられた山であるはずもなく、調べてみるとその逆だったようです。
Wikipediaによると、“名前の「野口」は、この山が属する長野県大町市の集落「野口」に由来し、「五郎」とは大きな石が転がっている場所を表す「ゴーロ」の当て字である”とのこと。
ということは、本当は「野口ゴーロ岳」なんですね。
富山以外の県の山々はどうなっているかと言うと、この後25位くらいに石川県から「白山<御前峰>(はくさん ごぜんがみね・2,702m)」が登場し、58位くらいに福井から「願教寺山(がんきょうじやま・1.691m)」が登場します。
これらはいずれも、「白山山地(加越山地)」に属する山だそうです。
山地が多すぎて何が何やら、もう訳わからんくなってきました(笑)
関西の高い山
さて、西日本に突入しましょう。まずは関西から。
| 山名<山頂名> | 標高 | 府県 | 所在地 | |
| 1 | 八経ヶ岳 はっきょうがだけ | 1,915m | 奈良 | 紀伊山地東部(大峰山脈) |
| 2 | 弥山 みせん | 1,895m | 奈良 | 紀伊山地東部(大峰山脈) |
| 3 | 仏生嶽 ぶっしょうがだけ | 1,805m | 奈良 | 紀伊山地東部(大峰山脈) |
| 4 | 釈迦ヶ岳 しゃかがだけ | 1,800m | 奈良 | 紀伊山地東部(大峰山脈) |
| 5 | 大普賢岳 だいふげんだけ | 1,780m | 奈良 | 紀伊山地東部(大峰山脈) |
| 6 | 山上ヶ岳 さんじょうがたけ | 1,719m | 奈良 | 紀伊山地東部(大峰山脈) |
| 7 | 大台ヶ原山<日出ヶ岳> おおだいがはらざん ひのでがたけ | 1,695m | 奈良(・三重) | 紀伊山地東部(大台原山とその周辺) |
| 8 | 氷ノ山 ひょうのせん(須賀ノ山 すがのせん) | 1,510m | 兵庫(・鳥取) | 中国山地東部 |
| 9 | 国見山 くにみやま | 1,419m | 奈良(・三重) | 紀伊山地東部(大台原山とその周辺) |
| 10 | 池木屋山 いけごややま | 1,396m | 奈良(・三重) | 紀伊山地東部(大台原山とその周辺) |
関西に入ると見えてくる西日本の大きな特徴は、最高峰の標高が2,000mを切るということです。(東海以北はすべて2,000m以上でした。)
そういう理由もあるのか、植生の違いも出てくるのか、東と西とでは自然風景の雰囲気がガラリと変わるような気が私はするのですが、どうでしょうか。
ともかく、上のランキングから分かることは、関西地方で高い山の集まる県は「奈良県」であるということですね。中でも「紀伊山地」がエースの山地のようです。
他にも、滋賀県北西部の「伊吹山地」、滋賀と三重の県境に位置する「鈴鹿山脈」、三重と奈良の間にある「高見山地」、京都府中部から兵庫にかけて広がる「丹波高地」など、いくつもの山塊があちらこちらにある様子。
かの有名な神戸の「六甲山」(931m)は、そのうちの一つ、「六甲山地」の主峰ですよね。あらためて地図で見ると、かなり海に近いところにあってびっくり。
この地形が「六甲颪(おろし)」を吹き降ろしたり、夏の暑さの原因になったりもするんだそうで。
颯爽と猛々しい存在として地元球団を応援する歌にもなっていることですし、いろいろ全部ひっくるめて土地の象徴になっているということが窺えますね。
紀伊山地に話を戻しますと、この山地の東寄りのエリアには「大峰山脈」という脊梁山脈がほぼ南北に走っており、北の「吉野山」から南の「熊野大宮大社」までの縦走ルートは世界遺産(紀伊山地の霊場と参詣道)ともなっています。(大峯奥駈道)
4年ほど前に熊野大宮大社近くで「瀞峡めぐり」をしたことがあるのですが、奈良市街からそこに至るまでの道のりは車であっても大変山深く、どこもかしこも360度山景色だったことが大変印象に残っています。

今でも女人禁制の修行場があったり(山上ヶ岳)、山の名前が仏教色満載だったり、かなり独特な空気感の漂うエリアですが、死ぬまでには一度、参詣道のどれかを歩いてみたいものです。
※世界遺産の参詣道については、こちらの「わかやま文化財ガイド」のページが地図付きで分かりやすいと思います。
中国地方の高い山
次は中国地方です。
| 山名<山頂名> | 標高 | 県 | 所在地 | |
| 1 | 大山 だいせん<剣ヶ峰> | 1,729m | 鳥取 | 中国山地中部 |
| 2 | 氷ノ山 ひょうのせん(須賀ノ山 すがのせん) | 1,510m | 鳥取(・兵庫) | 中国山地東部 |
| 3 | 烏ヶ山 からすがせん | 1,448m | 鳥取 | 中国山地中部 |
| 4 | 東山 とうせん | 1,388m | 鳥取 | 中国山地東部 |
| 5 | 三室山 みむろやま | 1,358m | 鳥取(・兵庫) | 中国山地東部 |
| 矢筈ヶ山 やはずがせん | 1,358m | 鳥取 | 中国山地中部 | |
| 6 | 恐羅漢山 おそらかんざん | 1,346m | 島根・広島 | 中国山地西部 |
| 7 | 後山 うしろやま | 1,344m | 岡山 | 中国山地東部 |
| 8 | 冠山 かんむりやま | 1,339m | 広島 | 中国山地西部 |
| 9 | 寂地山 じゃくちさん | 1,337m | 島根・山口 | 中国山地西部 |
| 10 | 十方山 じっぽうざん | 1,328m | 広島 | 中国山地西部 |
※大山の別の峰「弥山」の標高は1,709m。
中国地方はもう、ほぼ「中国山地」一択である様子。Wikipediaによると、兵庫県西部から山口県西部まで、約500kmにも及ぶ長い山地なんだそうです。
脊梁部はおおむね南北の県境に沿って走っており、脊梁部より北(山陰)は雪の多い「日本海岸気候」、南側(山陽)は雨が少なく温暖な「瀬戸内海式気候」。
広島と島根の県境付近は西日本のスノースポーツのメッカとなっており、「瑞穂ハイランド」や「芸北国際スキー場」、「恐羅漢スノーパーク」などがありますよね。
中国地方の最高峰、鳥取県西部にある「大山(だいせん)」は、正確には独立峰なのですが、中国山地の一部として扱われることも多いようです。

“伯耆(ほうき)富士”と呼ばれ親しまれるだけあって、きれいな富士山型をしていますよね。
大山もそうですが、中国地方の山々の名前を見ていて気になるのが、鳥取に「○○せん」と読む山が多いこと。鳥取ほどではありませんが、岡山や島根にも存在しているようです。
昔々、中国人でも住んでいたのか? 気になって調べてみると、この読み方は「呉音(ごおん)」という音読みの一種で、仏教用語でよく使われるそう。
大山のも宮島のもそうかもしれませんが、奈良の紀伊山地にも「弥山(みせん)」がありますし、仏教的な、信仰的な何かが理由なのかもしれません。が、はっきりしたことは分かっていないようでした。
山の名前って、いつ誰が決めたのか。土地の人が使っていた呼び名がいつしか定着するものなのか。掘り下げて調べてみると、いろいろ興味深いことが見えてくるかもしれません。
四国の高い山
次は、瀬戸内海を渡りましょう。
| 山名<山頂名> | 標高 | 県 | 所在地 | |
| 1 | 石鎚山 いしづちさん<天狗岳> | 1,982m | 愛媛 | 四国山地西部(石鎚山地) |
| 2 | 剣山 つるぎさん | 1,955m | 徳島 | 四国山地東部(剣山地) |
| 3 | 二ノ森 にのもり | 1,930m | 愛媛 | 四国山地西部(石鎚山地) |
| 4 | 瓶ヶ森 かめがもり | 1,897m | 愛媛 | 四国山地西部(石鎚山地) |
| 5 | 三嶺 みうね | 1,894m | 徳島・高知 | 四国山地東部(剣山地) |
| 6 | 笹ヶ峰 ささがみね | 1,860m | 愛媛・高知 | 四国山地西部(石鎚山地) |
| 筒上山 つつじょうざん | 1,860m | 愛媛・高知 | 四国山地西部(石鎚山地) | |
| 7 | 矢筈山 やはずさん | 1,849m | 徳島 | 四国山地東部(剣山地) |
| 8 | 天狗塚 | 1,812m | 徳島 | 四国山地東部(剣山地) |
| 9 | 白髪山 しらがやま | 1,770m | 高知 | 四国山地東部(剣山地) |
| 10 | 伊予富士 | 1,756m | 愛媛・高知 | 四国山地西部(石鎚山地) |
先ほどの中国山地よりも高い山々が多いようですね。
まず一番に気になるのが、「○○森」と名付けられた山がちらほらあること。
当記事のデータソースとしている国土地理院の「日本の山岳標高一覧」に載っている四国の「森」は全部で10ヶ所あり、うち6つは高知県でした。他は愛媛、徳島。
四国は特に多いように感じますが、東北など他のエリアにも「森」と名付けられた山はあります。
岩山でもなければまあ、山は森と言えば森ですけど…。こちらもネットで調べてみると、「森林・林業学習館」というサイトに以下のような記述がありました。
日本では「山」を「森」と同一のものとしていたようです。
日本人は古来より、入ることの困難な高くて大きな山(奥山や大きな森)には神が降り、神が宿る場所と考えてきました。
「神」の力によって木が自然に生え、盛り上がるように見えるのが、「森」と考えられそうです。
「森」と「林」の違い 森と神社
今度は仏教ではなく、神道に繋がった考え方ということでしょうか。とすれば、「セン」より古そうです。が、こちらも真相は不明。
四国のランキングはというと、香川県にはとりわけ高い山はないということが一番の発見です。同県の最高峰は、1,060mの「竜王山(りゅうおうざん)」です。
この竜王山は、香川と徳島の県境にある「讃岐山地(讃岐山脈・阿讃山脈)」に属しており、他にも愛媛に「高縄山地」という山地がありますが、四国で一番大きな山地と言えばやはり「四国山地」。
四国の中央を東西にどーんと寝そべっており、あの細い国道の数々から実感できる通り、ほんとに山深いですよね。美しいです。

年中温暖かと思いきや、山の方は意外と冬は雪が降るほどに寒く、スキー場もいくつもあります。これは、北からの冷たい空気によって凍った瀬戸内海の水蒸気が四国山脈にぶち当たるためなんだとか。
南国感もあり、雪もあり、海も山も渓谷もカルストも何でもありの四国。小さいのに大自然の魅力満載ですね。
【PR】アウトドア用品買うならエルブレス九州の高い山
ついに締めくくりの九州にやって来ました。
実は、私が前回と今回と2回に渡って“日本の山について調べてみようシリーズ”に乗り出した一番のきっかけは、これを調べたかったからなんです。九州の山ランキング。
大分北部の絶景展望台めぐりドライブについての記事を書こうとしたときに、知りたくなったのでした。
それではラスト、いってみましょう!
| 山名<山頂名> | 標高 | 県 | 所在地 | |
| 1 | 宮之浦岳 | 1,936m | 鹿児島 | 大隅諸島(屋久島) |
| 2 | 永田岳 | 1,886m | 鹿児島 | 大隅諸島(屋久島) |
| 3 | くじゅう連山<中岳> | 1,791m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
| 4 | くじゅう連山<久住山 くじゅうさん> | 1,787m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
| 5 | くじゅう連山<大船山 たいせんざん> | 1,786m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
| 6 | くじゅう連山<星生山 ほっしょうざん> | 1,762m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
| 7 | 祖母山 そぼさん | 1,756m | 大分・宮崎 | 九州山地 |
| 8 | くじゅう連山<三俣山 みまたやま> | 1,744m | 大分 | 阿蘇・くじゅうとその周辺 |
| 9 | 国見岳 | 1,739m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
| 10 | 市房山 いちふさやま | 1,721m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
| 11 | 霧島山<韓国岳>きりしまやま からくにだけ | 1,700m | 宮崎・鹿児島 | 九州南部 |
| 12 | 向坂山 むこうざかやま | 1,685m | 熊本・宮崎 | 九州山地 |
| 13 | 上福根山 かみふくねやま | 1,646m | 熊本 | 九州山地 |
| 14 | 大崩山 おおくえやま | 1,644m | 宮崎 | 九州山地 |
| 15 | 古祖母山 ふるそぼさん | 1,633m | 大分・宮崎 | 九州山地 |
大雪山一味が席巻した北海道と同じく、くじゅう連山一味が5枠も取ってしまった九州も、特別にトップ15といたしました。
ご存じの方も多いと思いますが、1位と2位は鹿児島県の屋久島にあります。
同島の属する「大隅諸島」や「奄美群島」など、島にある高い山々は全て火山なのかと思いきや、火山によるものもあれば、隆起や浸食によるものあるようです。
ちなみに宮之浦岳は、“四国海盆の沈み込みにより生じた花崗岩が、隆起と侵食を受けて、高く険しい山地を形成したと思われる”んだとか。(Wikipedia「南西諸島」より)
九州本土の方に目を向けると、ざっくりとは阿蘇を挟んで北の「くじゅう連山」と南の「九州山地」、さらに南の「霧島山地(火山群)」に高い山が集まっている様子。
九州山地はまるで南東の宮崎県を切り離すかのように連なっており、その往来の不便さから宮崎は“陸の孤島”なんて呼ばれたものです。
また、全国的に有名な熊本の「阿蘇山」は、高さとしては実はトップ15には入りません。(阿蘇五岳で一番高い「高岳」は1,592mで18位。)

私をはじめとする多くの九州人が謎に思っているかもしれない「くじゅう・九重・久住、どれがどうなのか問題」については、“火山群や周辺地域全体を指す場合に「くじゅう連山」や「九重連山」を用い、その主峰である単独の山を指す場合に「久住山」を用いるのが一般的”だそうです。(竹田市公式サイト「緑の大自然(くじゅう連山)」より)
裏話として、昔は「九重」か「久住」かで統一はされていなかったところ、市町村合併によって周辺に「九重町(ここえまち)」と「久住町」ができ、どちらの漢字を使うかでもめた…というようなことがネット上にはちらほら書いてありました。
しかし実際現地に行くと「久住高原」という看板が立っていたりして、今でも紛らわしいことに違いはありません。
高原感満載の「やまなみハイウェイ」沿いには数々の展望台、登山口、ラムサール条約湿地「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」などもありますし、今年の夏はゆっくり出かけてみようかな☺
おわりに
以上、日本のエリアごとの「高い山ランキング」をお送りいたしました!
ランキングは元データを慎重に扱って作成しておりますが、順位も飛ばさずにカウントしていることですし、内容はあくまで“私調べ”ですので、話半分でお楽しみいただけたなら幸いです(笑)
前回の記事も含めて2記事分、エクセルと格闘すること5日間でようやく完成しましたので、私事ですが、とりあえず達成感でいっぱいです。
1059の山(峰)の名前を見てきて、面白いな、変わってるな、と思うものもたくさんありました。
例えば南アルプス北部の「新蛇抜山 しんじゃぬけやま」、南アルプス南部の「光岳 てかりだけ」、岐阜・滋賀の「金糞岳 かなくそだけ」、大分の「酒呑童子山 しゅてんどうじやま」、丹波高地の「ポンポン山」…。
妙高山周辺の「雨飾山 あまかざりやま」、兵庫の「来日岳 くるひだけ」、南アルプス南部の「布引山 ぬのびきやま」など、風情があるなぁとなんとなくいい気分になった名前もありましたし。
駒ヶ岳、朝日岳、黒岳など、各地で人気のネーミングもあったり。
おかげさまで、また日本中を旅して回って、山の名前を認識した上でたくさん写真を撮りたい!という今後の希望もできました☺
みなさまの、何かしらの山に関する活動も、陰ながら応援していますよ!
最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。
それでは! Polly